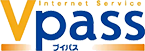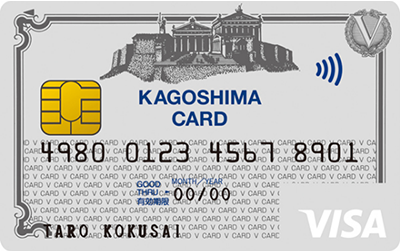その他のサービス
本が売れなくなったと言われて久しい現代ですが、その中でミステリー関連の書籍は世界市場でも当面は拡大が予想されている数少ない分野です。
そんなミステリー小説は、1841年にエドガー・アラン・ポーが「モルグ街の殺人」を発表して以来、古今東西数々の傑作が生み出され、今も多くの人々に読み継がれている名作があるのは御存じの通りだと思います。しかしながら、その名作の中にも以前ほど注目されず、なかば忘れられかけている作品があるのも事実です。
今回は(次回があるのか?)は、そんな埋もれかけた名作の中から、謎解き本格ミステリーの古典作3冊を選び、皆さんにご紹介したいと思います。
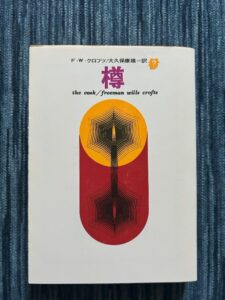
一冊目はイギリスのF・W・クロフツ作『樽』(The Cask, 1920)です。あらすじは字数の関係上省略しますが、犯人により綿密に仕組まれたアリバイを少しずつ崩していく醍醐味に加え、従来の天才型探偵(ひらめき型)を排し凡人型探偵(コツコツ型)を起用することで小説にリアリティももたらされています。クロフツは、もう少し再評価されてもいいのではと常々思っている作家の一人です。
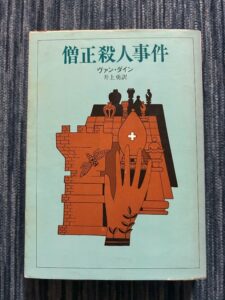
二冊目はアメリカのヴァン・ダイン作『僧正殺人事件』(The Bishop Mnrder,1929)です。童謡のマザー・グースの歌詞どおりに殺人が次々に起こるという内容で、日本のミステリー黎明期の作家に大きな影響も与えています。名探偵ファイロ・ヴァンスの(少々鼻につきますが)無類の博識ぶりと心理分析を駆使した天才的な活躍も、ミステリー小説黄金時代の香りが十分感じられます。
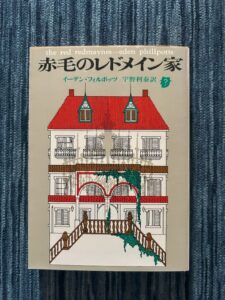
三冊目はイギリスのイーデン・フィルポッツ作『赤毛のレドメイン家』(The Red Redmaynes,1922)です。かの江戸川乱歩が初めて読んだ際に狂喜したと言われるクラッシック名作。
本書の特徴として、プロットの巧緻さ、何重にも仕組まれたトリック、犯人の執念の恐ろしさ、等が挙げられますが、当時のミステリーとしては珍しく"恋愛"が物語展開に重要な役割を与えてもいます。その分、それまでパズル文学と揶揄されがちだったミステリーを立派な文学としての位置づけへと導いた本書は、歴史的にも貴重な作品であったと思います。

翻訳小説は読みにくいと思っている方も多いでしょうが(事実、以前はそうでした)、今回の三冊とも新訳版がでていますので(いずれも東京創元社「創元推理文庫」)、興味のある方は是非手にとっていただき、古き良きミステリーの世界を体感されてみては。